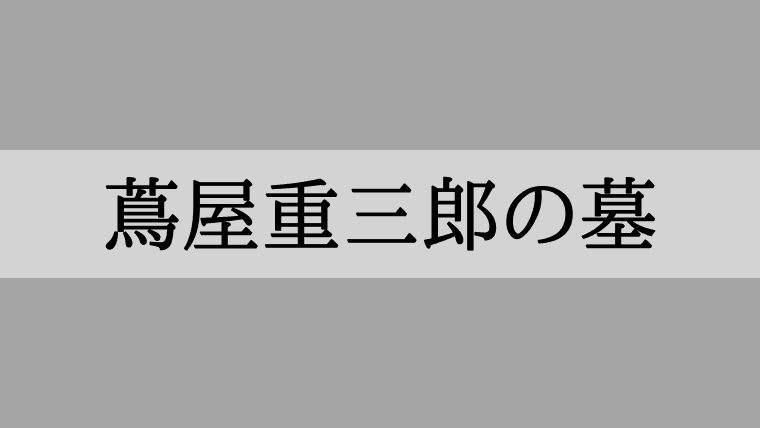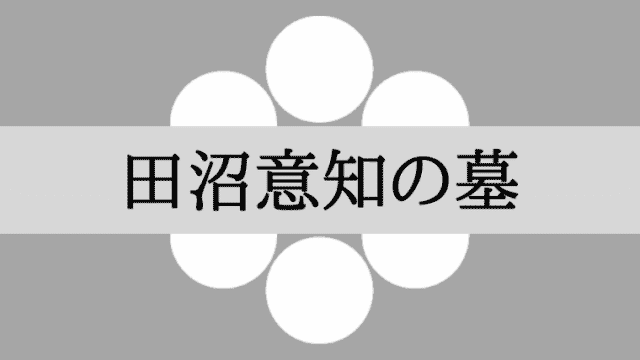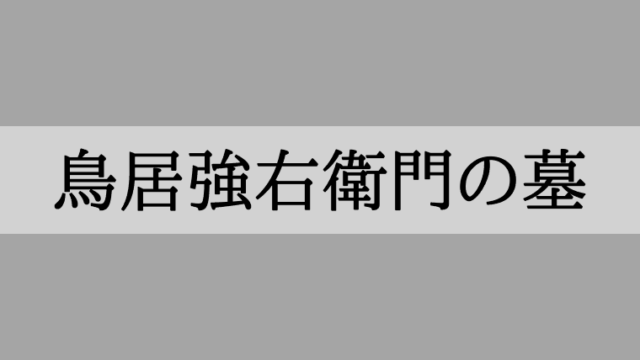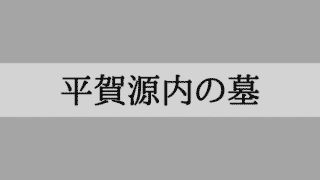江戸時代中期に町人文化の中心で活躍した伝説的出版人「蔦屋重三郎」の墓は、東京都台東区の「正法寺(しょうぼうじ)」にあります。
誠向山正法寺(せいこうざんしょうぼうじ)
| 墓所 | 誠向山正法寺(せいこうざんしょうぼうじ) |
|---|---|
| 住所 | 〒111-0025 東京都台東区東浅草1-1-15 |
| アクセス | 東京メトロ銀座線「浅草駅」から徒歩約15分。 |
初代・蔦屋重三郎が眠る墓所が「正法寺(しょうぼうじ)」です。
墓碑には、蔦重の本名「喜多川柯理(きたがわ・からまる)」を刻んだ「喜多川柯理墓碣銘」と彫られています。近年では、浮世絵ファンや大河ドラマファンなどの参拝者も多く訪れています。
公式サイト>>誠向山正法寺
蔦屋重三郎の生没年・戒名・家紋データ
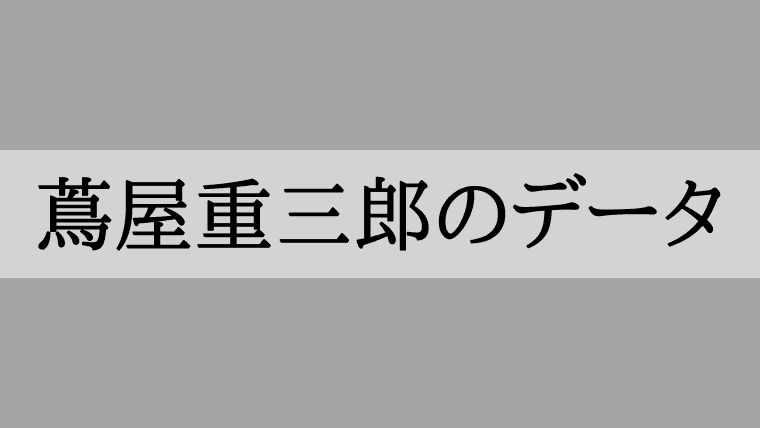
| 生年 | 寛延3年(1750年) |
|---|---|
| 没年 | 寛政9年(1797年) |
| 命日 | 旧暦5月6日、新暦5月31日 |
| 享年(数え) | 48歳 |
| 死因 | 病死 |
| 戒名 | 幽玄院義山日盛信士 |
| 家紋 | 富士山形に蔦の葉(版元印) |
蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)とは?
初代・蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)は、江戸時代中期に活躍した出版人であり、浮世絵・洒落本・黄表紙などを世に送り出した江戸文化の立役者である。町人文化の黄金時代を築いた先駆者として、「江戸のメディア王」とも称される。
1750年、新吉原(現・東京都台東区千束)に生まれ、7歳で両親が離婚。引手茶屋「蔦屋」を営む喜多川家の養子となる。1772年、23歳のときに吉原大門口に書店「耕書堂」を開き、出版業へと歩み出す。以後、『吉原細見』や北尾重政の『一目千本』などを手がけ、版元としての地位を確立していく。
1780年代には、狂歌や黄表紙、洒落本などが流行し、大田南畝・山東京伝・恋川春町・朋誠堂喜三二ら人気作家と手を組み次々とヒット作を刊行。吉原の案内書からパロディ文学まで、重三郎の企画力と編集力が冴え渡り、出版事業は絶頂期を迎える。1783年には店舗を日本橋通油町(現在の中央区大伝馬町)にも展開し、一流の書肆として名を馳せた。
しかし、1787年に始まった「寛政の改革」により風紀取締りが強化され、1791年には出版物が問題視され罰金刑を受ける。だが蔦重は屈せず、1793年には喜多川歌麿による美人大首絵シリーズ『歌撰恋之部』を、1794年には東洲斎写楽による役者絵を刊行し、浮世絵界に新たな風を吹き込んだ。
1796年、蔦重は「江戸患い(脚気)」により病床に伏し、翌1797年に48歳で没した。没後は番頭・勇助が二代目を継ぎ、蔦屋は四代目まで続くことになる。
蔦重の最大の功績は、単なる出版業にとどまらず、文化と情報を編み出し、庶民に届けた点にある。多色刷りの印刷技術や革新的な装丁により、読書と鑑賞を一体化させた出版物を創出し、江戸の町人文化を花開かせた。「喜多川歌麿」や「葛飾北斎」など、後世に名を残す芸術家たちの才能を見出した重三郎の慧眼は、現代においても高く評価されている。
関連墓所
蔦屋重三郎の堂号「耕書堂」は、平賀源内が名付けたとされています。