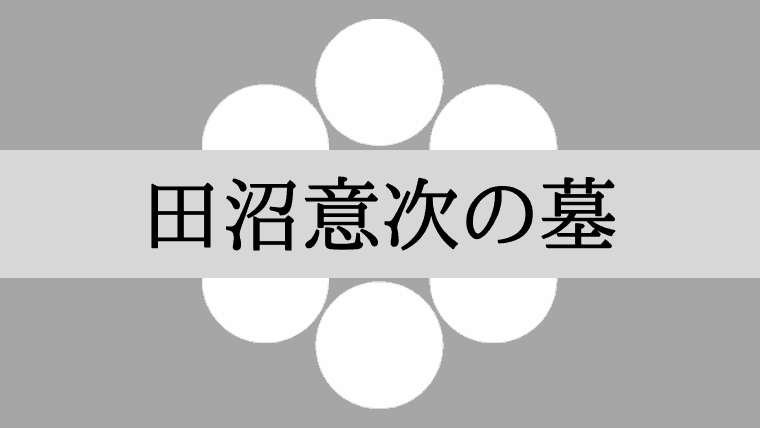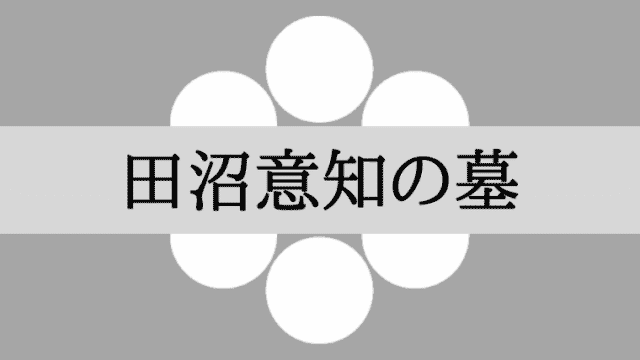江戸後期、田沼時代を築いた江戸幕府老中「田沼意次」の墓は、東京都豊島区の「勝林寺(しょうりんじ)」にあります。
萬年山勝林寺(まんねんざんしょうりんじ)
| 墓所 | 萬年山勝林寺(まんねんざんしょうりんじ) |
|---|---|
| 住所 | 〒170-0003 東京都豊島区駒込7-4-14 |
| アクセス | JR山手線「駒込駅」「巣鴨駅」から徒歩約15分 |
勝林寺は田沼家の菩提寺で、意次のほか嫡男・田沼意知など一族の墓が並んでいます。境内には「田沼意次の墓」と刻まれた墓碑があり、田沼時代の盛衰を今に伝えています。
公式サイト>>萬年山勝林寺
田沼意次の生没年・戒名・家紋データ
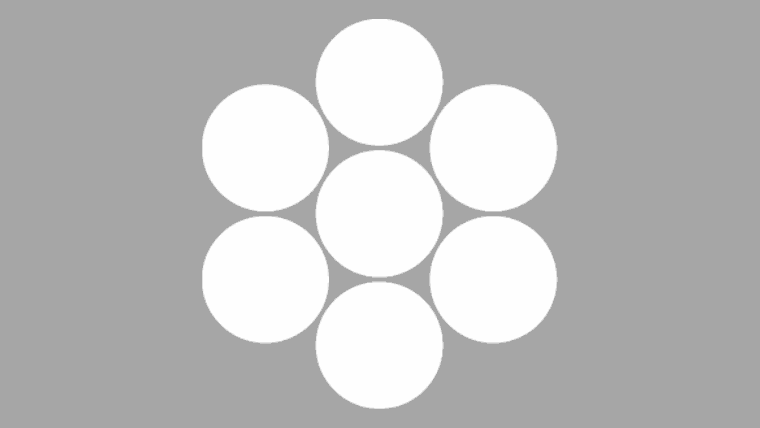
| 生年 | 1719年(享保4年) |
|---|---|
| 没年 | 1788年(天明8年) |
| 命日 | 旧暦7月24日、新暦8月25日 |
| 享年(数え) | 70歳 |
| 死因 | 病死 |
| 戒名 | 隆興院殿耆山良英大居士 |
| 家紋 | 七曜 |
田沼意次(たぬま・おきつぐ)とは?
田沼意次(たぬま・おきつぐ)は江戸時代中期から後期に幕政を担い、賄賂政治と批判されつつも、近年では合理的な経済政策を進めた名宰相として再評価されています。
1719年(享保4年)、紀州藩の足軽から旗本となった田沼意行の長男として生まれ、低い身分ながら才覚を発揮し幕府の中枢へ登りつめました。
8代将軍・徳川吉宗の治世から頭角を現し、9代将軍・徳川家重の信任を得て側用人から老中へと異例の昇進。その後、10代将軍・家治のもとで老中首座となり、幕政を事実上主導しました。
田沼意次の政治は、農本主義からの転換を図る重商主義的政策が特徴です。株仲間(商人組合)の奨励や長崎貿易の拡大を進め、貨幣経済を活用して幕府財政の立て直しを試みましたが、賄賂や腐敗の横行も批判されました。
失脚の要因となったのは、1782年からの天明の大飢饉や浅間山噴火による凶作に加え、嫡男・意知が江戸城内で襲撃される事件が起きたことです。
最終的に老中を罷免され蟄居を命じられ、駿河国田中藩で隠居生活を送り、1788年(天明8年)に70歳で病没しました。その後、松平定信の質素倹約と農村復興を重視する「寛政の改革」で田沼時代の政策は改められました。
関連墓所